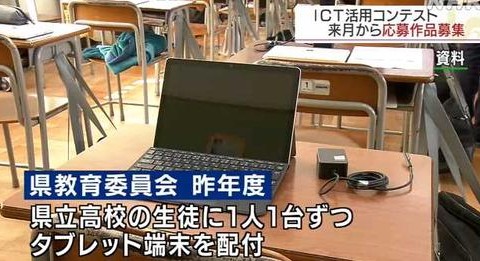国税庁のDX戦略の柱と噂されるKSK(国税総合管理システム)。「国税庁はAIを使って調査対象者を探し出す」だとか、「KSKがはじき出した理論値と大きな乖離がある者を選び出す」などの都市伝説がまことしやかに流れている。しかし、KSKには調査対象者を見つけ出す機能は備わっていないため国税職員は鼻で笑っている。本稿では、実際の調査現場ではどのようにして調査対象者を選び出しているのか、さらに2022年に狙い撃ちされそうな業界を紹介したい。(元国税査察官・税理士 上田二郎)
なぜAI調査の都市伝説が生まれたのか?
先日、ある週刊誌の記者から「税務調査の特集を組むので、どのように調査対象者を選び出すのかについて、特にAIを搭載したKSKの能力について教えてほしい」との取材依頼があった。筆者は「調査の選定は経験と感性が重要で、KSKにはそんな能力はないよ」と答えたのだが、その少し前にも別の週刊誌記者から同じ質問をされている。
国税庁の発表によれば、AIを使って対象企業を選び出す新システムは大企業が対象となる。公表されている財務資料や会社の業績を説明する音声データを分析し、脱税の疑いがある会社を絞り込むという。しかし、こんなもので脱税者が見つかるなら調査官は苦労しない。
新システムは、実際にあった脱税や申告漏れの手口をAIに学習させ、公開の財務資料を分析させるとのことだが調査は常に後追いだ。時流に乗った会社が大もうけをしたものの、納税資金が惜しくなって申告額を細工するのだが、調査に入るのは3~5年後。脱税の手口を見つけ出したときには、すでにその手口は古くなっている。
そもそも、利益を稼ぎ出すこと自体もワンパターンではなく、脱税手段も千差万別のため、調査対象者の抽出には他社との比較や過去のデータは役に立たない。さらには、大企業には公認会計士や税理士が関与しているため、もし前年の申告データと比較して異常数値があるなら、原因を追究してから申告書を提出する。
また、決算説明会に出席した経営陣の音声データや、年次事業報告に掲載された経営トップの写真やメッセージを分析するとのことだが、こうなってくるともはや占い並みだ。
AIに頼る背景には調査官の劣化があるのだろう。OBとして税務調査で対峙すると、あまりの調査能力の衰えに悲しみすら覚える。:ダイヤモンドONLINE
国税関係業務の業務・システム最適化計画2012年(平成24年)2月10日改定:財務省行政情報化推進委員会決定
第1 業務・システムの概要
国税庁は、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達及び税理士業務の適正な運営の確保を図ることを任務としている。
その任務を果たすため、国税関係業務は、申告書等の収受、申告書の処理、申請書・届出書等の処理、納税者管理、収納・還付、滞納整理、調査・指導、犯則の取締り、資料情報の収集・管理、税務一般に関する相談等の業務により構成されている。
これらの一連の業務には、国税総合管理システム(以下「KSKシステム」という。)、国税電子申告・納税システム(以下「e-Tax」という。)、集中電話催告システム、タックスアンサーシステム等のシステムが利用されている。
国税関係業務・システムの最適化に当たっては、IT化の一層の推進により効率化を図る観点から、各システムのみならず、システムに関連する業務の見直しも行うこととし、丸1業務を的確に実施するための事務処理の簡素化・効率化、丸2IT活用による納税者利便性の向上等、丸3IT活用による調査・滞納整理に関するシステムの高度化、丸4システムの安定性・信頼性及び情報セキュリティの確保及び丸5システム関係経費の削減及び調達の透明性の確保を図ることをその基本理念とする。
第2 最適化の実施内容
国税関係業務・システムについて、次に掲げる最適化を実施する。
この結果、年間約173億円の経費削減(試算値)及び年間延べ約137,000人日分の業務処理時間の短縮(試算値)が見込まれる。
これにより、行政運営の簡素化、業務効率の向上を図るとともに、適正かつ公平な賦課及び徴収の実現という国税庁の任務を的確に果たすため、税務調査や滞納整理の一層の充実を図り、納税者のコンプライアンス向上を目指す。
1 業務を的確に実施するための事務処理の簡素化・効率化
国税庁においては、法人数及び所得税申告者数の増加や制度改正等による申告者数の増加などにより申告・納税の事績管理等の事務が恒常的に増加している。加えて、経済取引の広域化・国際化により事務が多様化、複雑化している。
また、行政に対するニーズの変化に伴い、情報公開に係る事務量や納税者への対応に要する事務量も増加している。
これに対し、国税庁は、従来からシステム化による効率化やアウトソーシングの積極的な推進に努めてきたが、限られた定員の下でこれらの事務を的確に処理できるよう、次のとおり、更なる簡素化・効率化に取り組む。
(1) 内部事務の一元化
従来、税務署においては、国税庁の所掌事務が「内国税の賦課及び徴収に関すること」とされていることを踏まえ、賦課事務(課税内部事務、調査事務等)と徴収事務(債権管理事務、滞納整理事務等)を別々の部門で所掌していた。
しかしながら、賦課事務のうちの課税内部事務(申告書の情報の入力事務等)と徴収事務のうちの債権管理事務(収納・還付事務等)は、共に内部事務であり、かつ、密接に関連することから、これらを一つの部門(管理運営部門)で一体的に処理することで効率化を図った。
このため、必要となる法令上の手当てを行うとともに、事務処理手順の統合・標準化を図り、併せてシステムの修正を行った。
具体的には、1一般税務相談、2納税者管理(転出入処理等)、3申告書等の収受、4申告書の発送、入力、5収納・還付、6納税証明書の発行などを一体的に処理し、事務の効率化に取組んだ。
今後も引き続き、内部事務の一元化等を踏まえ、類似した業務について、システム上の処理を統合するなど、事務の効率化を図っていく。
(2) 電子データの有効活用等による事務の簡素化・効率化
国税庁の事務が納税者の権利・義務に直接影響を及ぼすものであることに十分配意しながら、システムを活用して事務処理の簡素化・効率化を図っていく。
イ 地方公共団体と書面で連絡している所得税の確定申告書等の各種税務関連情報を相互にデータ送信することにより、申告書の管理などの事務を効率化する。
ロ e-Taxにより提出される申告書等について、電子データを活用し、KSKシステムへ自動でデータ連絡を行うなど、申告書等の入力事務等の簡素化に引き続き取組む。
ハ 調査支援資料について、データによるアウトプットを可能とし、調査事務に係る二次分析のための入力事務の軽減を図るなど、効率的なデータ活用を推進する。
ニ 電子データを活用し、税務署の部門間の連絡手段を書面からデータに変更するなどにより、事務処理の効率化を図る。
ホ 多様なニーズへの対応を可能とするために、e-Taxにおいて保有する情報の高度活用を検討する。
ヘ その他、次の取組により、事務処理の簡素化・効率化を図った。
(イ) 還付金を未納の国税へ充当する処理等の一部自動化(平成16年度)(※カッコ書きは実施年度。以下同じ。)
(ロ) 所得税申告書のKSKシステムへの全件入力による申告書の分類・整理等の事務の簡素化(平成17年度)
(ハ) 訂正入力事務の簡素化(平成17年度)
(ニ) 振替納税のためのMT交換処理の国税庁への集中化(平成17年度)
(ホ) 不動産鑑定士等から提出される土地の意見価格調書の電子化による入力事務の簡素化(平成19年度)
(ヘ) 国税還付金等の支払決議書の電子化による税務署における会計検査院への支払決議書の送付等の事務の効率化(平成19年度)
(ト) KSKシステムが保有する情報の活用による大規模法人の調査関連書類の作成事務の効率化(平成21年度)
(チ) 法人税確定申告書等のモノクロOCR用紙の仕様を公開し、納税者のプリンタから出力されたモノクロOCR用紙での提出を可能とすることによる申告書等の入力事務の簡素化(平成21年度)
(リ) e-Taxデータの統計事務への活用による調査票等の入力事務の簡素化(平成22年度)
(3) 事務の集中化、アウトソーシングの推進
スケールメリットによる効率化を図るため、事務の集中化を図る。
具体的には、税務署に寄せられる電話相談のうち、一般的な税務相談を電話相談センタに集約し、電話相談事務を効率化した(平成20年度)。
また、他の事務とは独立し、一時に大量に発生する事務等について、更なる事務の集中化及びアウトソーシングの推進を検討する。
2 IT活用による納税者利便性の向上等
今後とも、納税者の視点に立って、次の取組を実現することにより、IT活用による納税者利便性の向上等を図る。
特に、電子政府の推進のため、「新たなオンライン利用に関する計画 (平成23年8月IT戦略本部決定)」、「電子政府ユーザビリティガイドライン(平成21年7月各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)」及び「オンライン手続におけるリスク評価及び電子署名・認証ガイドライン(平成22年8月各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)」に基づき、e-Taxの利用拡大に積極的に取り組み、併せて業務の効率化についても検討する。
(1) e-Taxの機能・運用の改善
e-Taxについては、平成16年2月の導入以来、対象手続及び受付時間の拡大、税理士関与の場合に納税者本人の電子署名を省略するなどの一部電子署名の省略、e-Taxソフトのダウンロード方式による配付、早期還付によるインセンティブ措置、確定申告期間における24時間受付、所得税の電子申告における第三者作成書類の添付省略、税務署設置の端末機からの電子申告など機能・運用の改善に取り組むとともに、積極的な広報・周知に努めてきた。
今後も、税理士会や関係民間団体を通じた電子申告研修会の実施などに取り組み、e-Taxの普及に努めるとともに、メッセージボックスへの送信内容の充実、贈与税に係る電子申告の導入など更なるe-Taxの機能・運用の改善を図る。
(2) 国税庁ホームページ(「確定申告書等作成コーナー」)の機能改善
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」については、株式譲渡や先物取引等の所得に係る申告書作成機能を追加し(平成15年度)、青色申告決算書等の作成機能、個人事業者の消費税等確定申告書作成機能も追加した(平成16年度)ほか、同「作成コーナー」からe-Taxへの直接送信、贈与税申告書の作成機能を追加した(平成18年度)。さらに公的個人認証以外の電子証明書を利用したe-Taxへの直接送信機能を追加した(平成19年度)。
(3) 納税者窓口関係事務の一本化(ワンストップサービス)の推進
税務署への来署者が複数の用件に関して短時間で目的を達成できるよう、納税者窓口の一本化(ワンストップサービス)を全国税務署に導入した(平成21年度)。
(4) 還付金振込処理の迅速化
国税庁と日本銀行間の国税還付金振込の情報連絡をオンライン化し、納税者の預貯金口座への振込を迅速化した(平成18年度)。
(5) 国税の納付手段の多様化
国税の納付手段として、金融機関又は税務署窓口での納付、口座振替による納付、インターネットバンキング等を利用した電子納付に加え、コンビニエンスストアでの納付(平成19年度)、インターネットバンキングを経由しない電子的な納付手続であるダイレクト納付(平成21年度)を導入した。
(6) 公売事務におけるインターネットの活用
公売財産について、インターネットを活用した情報提供を行った(平成18年度)。その活用状況を踏まえ、電子入札システムなど、公売参加者のニーズに的確に対応できるシステムの構築を検討する。
3 IT活用による調査・滞納整理に関するシステムの高度化
経済社会の国際化・高度情報化が進展する中で、適正・公平な課税を確保するため、国際的租税回避スキームや電子商取引など先端分野への対応、広域的に事業展開する企業グループの対応などが強く求められている。
このような中で、調査・滞納整理の一層の充実を図るため、情報セキュリティに配意しつつ、次の取組により、国税関係システムの高度化を図る。
さらに、e-Taxの普及により蓄積される電子データが増加することから、こうしたデータの有効活用による更なる事務の高度化について検討する。
(1) 納税者に関する各種情報の相互活用等
納税者間の取引関係が多様化・広域化しており、これに対応するため、関連する情報を一体的に把握するとともに、金融資産や不動産等の資産情報を的確に把握する必要が高まっている。
このため、各部署が保有する情報の相互活用を図り、納税者の様々な情報をシステム上一元的に管理することにより、効率的な調査を行う。
(2) 調査選定における財務データ等の高度活用
所得税青色申告決算書及び収支内訳書の記載事項の充実、財務データの統計的手法に基づく分析システムの開発などによる調査選定事務の充実について検討する。
(3) 査察に関するシステムの高度化
KSKシステムとOAシステムで二元管理されている資料情報を一元化するなど、査察に関するシステムの高度化を図った(平成22年度)。
(4) 間接諸税・酒類関係に係るシステムの整備
間接諸税の犯則取締事務について、各国税局が保有する情報をデータベース上で共有化するシステムを構築し、情報の効果的な活用を図った(平成21年度)。
また、酒類関係に係るシステムについては、KSKシステムとOAシステムで二元管理されている情報を一元化した上で、酒類業者の経営状況等の分析を自動化し、情報の効果的な活用を図った(平成21年度)。
(5) 滞納整理に関するシステムの整備
消費税の新規課税事業者の増加に対応するとともに、悪質・処理困難事案に対してより厳正な処理を行うため、滞納事案に関する各種情報の管理・分析をシステム化し、的確な進行管理や処理展開を行う。
(6) 資産課税に関するシステムの整備
譲渡所得に関する調査対象を効率的に選定するための機能を開発するなど、資産課税に関するシステムの高度化を図る。
4 システムの安定性・信頼性及び情報セキュリティの確保
国税関係業務は、国民の権利義務と密接に関わっているため、そのシステムに障害が発生した場合には、国民に多大な影響を与え、税務行政に対する信頼を失うことになる。このため、国税関係システムの安定的な運用と納税者データの信頼性の確保に万全を期する必要がある。
また、国税関係システムは、大量の納税者情報を保有・蓄積することから、不正利用や漏えいの防止には万全の注意を払う必要がある。このため、職員は職務上必要な情報しか利用できない仕組みにするほか、情報セキュリティ訓令を定めてその徹底を図るなど、セキュリティの確保に努めている。
今後、データ量やシステムに対する負荷などを踏まえた適切なシステム構成となるよう配意しつつ、次の取組により、更なるシステムの安定性・信頼性及び情報セキュリティの向上を図る。
(1) システムの安定性・信頼性の確保
イ バックアップセンタの設置
自然災害等により長期間システムが停止した場合にも納税者や税務行政に支障が生じないよう、KSKシステムのうち、基幹となる業務システムについて、バックアップセンタを設置した(平成17年度)。
なお、バックアップ用ホストコンピュータは、平常時はシステム開発用及び研修用として利用している。
また、東日本大震災を受けて、KSKシステムやe-Taxを含めた国税関係システム全体のバックアップの在り方について検討する。
ロ システム機器の定期的なリプレースの実施
システム機器の定期的なリプレースを実施し、システムの安定性・信頼性を確保する。
KSKシステムについては、ホストコンピュータのリプレースを実施した(平成17及び22年度)。
e-Taxについては、平成23年度にリプレースを実施する。
集中電話催告等のその他のシステムについても、順次、定期的にリプレースを実施する。
なお、リプレース時には、技術進歩や価額の低下を取り込むことにより、経費削減を図る。
(2) 情報セキュリティの確保
イ 端末機等のセキュリティの向上
端末機について、格納データの暗号化、パスワード付暗号によるデータ取出し、生体認証の導入等により、セキュリティの向上を図った(平成22年度まで)。
今後、技術動向を踏まえ、端末機、データ保管媒体の紛失等によるデータ漏えいの防止のため、シンクライアント化・サーバ集中化などを検討し、一層のセキュリティの向上に取り組む。
ロ センタ施設等のセキュリティの向上
国税関係システムを集中的に管理するセンタ施設及びバックアップセンタについて、国際的標準規格に準拠した情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価に基づくISO認証を取得しており、ISO認証の維持のため、年1回の外部業者による維持審査(3年に1回の更新審査)を実施し、その結果を踏まえて必要な対策を講じている。
また、国税庁・国税局のセンタ間あるいはセンタと外部との間のデータ搬送について、搬送データの暗号化・電送化を推進する。
ハ ネットワーク構成の見直し
OAシステムのネットワークをインターネットから分離した(平成17年度)。
5 システム関係経費の削減及び調達の透明性の確保
国税関係システムについては、システム全体の視点に立って重複する機能を見直し、機器の再編成・統合の推進等によりシステムの効率化と経費削減に努めるとともに、一般競争入札の拡大等による調達の透明性の向上を図る必要がある。
このため、次の取組により、システムの更なる効率化と経費削減を図るとともに、システム開発、機器の調達等について一般競争入札の対象範囲を拡大する。
(1) システムの効率化と経費削減
イ KSKシステムとOAシステムの統合
セキュリティに留意しつつ、KSKシステムとOAシステムのネットワーク、通信回線及び端末機を統合した(平成18年度まで)。
ロ KSKシステムの刷新
(イ) 段階的なオープンシステム化の推進
外部専門家による「国税総合管理(KSK)システムに係る刷新可能性調査」(平成15年度)の結果、システムを構成する24の業務システムのうち、14の業務システムはオープンシステム化が適しており、経費削減が見込まれるとされた。
これを踏まえ、14の業務システムについて、段階的なオープンシステム化を行い、オープンシステム化に当たっては、汎用パッケージソフトウェアの活用による経費削減を図る。
1 税務相談、課税事績検索、総務(税理士)、審理室、鑑定の5業務システムをオープンシステム化した(平成17年度)。
2 非課税貯蓄限度額管理及び会計の2業務システムをオープンシステム化した(平成18年度)。
3 機器のリプレースに併せて、資料調査、財産評価、業務管理情報、企画及び査察の5業務システムをオープンシステム化した(平成22年度)。
4 府省共通業務システムに併せて、人事及び厚生の2業務システムをオープンシステム化する。
残りの10業務システムのうち、徴収システムについては、平成18年度までの検討状況を踏まえ、オープンシステム化の開発を完了した(平成22年度)。
他の9業務システム(納税者情報、所得税・消費税、法人税・消費税、資産税、源泉所得税、債権管理、調査、酒税、間接諸税)は、納税者の権利義務に密接にかかわり、高い安定性・信頼性が必要であるため、現時点では各システムすべての機能をオープンシステム化することは困難と考えられる。
残りの機能についても引き続き、今後の技術動向を踏まえ検討を進める。
(ロ) ソフトウェアの汎用製品化の推進
KSKシステムの端末機等のソフトウェアについて、平成17年度以降順次、汎用性のある製品に切替え、他のシステムとの操作性の統一と経費削減を図る。
ハ 機器の再編成・統合の推進
タックスアンサーシステムについて、機器の集約化、利用件数に応じた回線数の見直し等を行い、経費削減を図った(平成17年度)。
現金領収については、国税の納付に係る現金領収(国税資金)と各種手数料に係る現金領収(一般会計)をそれぞれ専用レジスターにおいて行っていることから、専用レジスターの統合を行い、経費削減を図る。
なお、所得税申告書のKSKシステムへの全件入力に伴い、源泉所得税還付金(個人)システムの機器を廃止した(平成17年度)。
集中電話催告システムについて、センタへのサーバの集約、KSKシステムとのオンライン化を行い、経費削減を図った(平成21年度)。
KSKシステムの機器のリプレースを行う際に、ホストコンピュータの機器構成を見直すとともに、国税局及び税務署に設置されているサーバを統合し、経費削減を図った(平成22年度)。
e-Taxについて、リプレースの際に機器構成の見直しや機器性能の精査を行い、経費削減に努める。
(2) 調達の透明性の確保
イ 一般競争入札の対象の拡大
国税関係システムの調達単位について、機器、システム開発等を細分化し、一般競争入札の対象を拡大する。
その際、システム開発等の調達を複数年にわたって行う必要がある場合には、引き続き、国庫債務負担行為を活用した複数年契約を推進する。
ロ プロジェクトマネジメントにおける外部専門家の活用
国税関係システム全体を適切に管理(プロジェクトマネジメント)し、システムの効率性の確保及び調達手続における透明性の向上を図るため、調達側の立場に立って支援を行う外部専門家を活用する(平成16年度から)。
「国税関係業務の業務・システム最適化計画」(本文)(PDFファイル/339KB)
第3 最適化工程表
別紙のとおり。(PDFファイル/197KB)
第4 現行体系及び将来体系
別添のとおり。
(参考)
経費の削減効果(試算値)及び業務処理時間の短縮効果(試算値)は、実施する施策ごとに、その実施後におけるシステムの運用管理に係る4年間の必要経費及び業務処理時間を推計した上で、現行のシステムの運用管理に係る4年間の必要経費及び業務処理時間と比較し、その差分(年平均額及び時間)を示したものであって、実際の効果は変動しうる。
https://www.nta.go.jp/information/attention/data/saitekika/02.htm