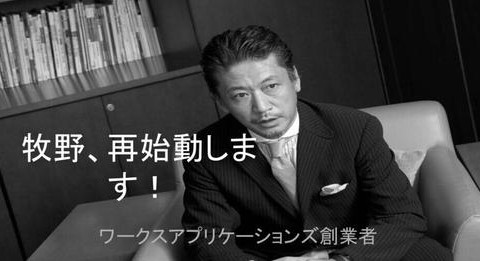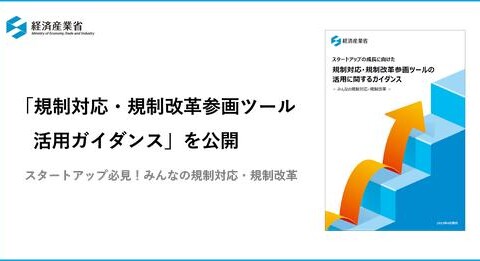日立造船は社会的なDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の追い風を受けて、デジタル人材の育成に取り組んでいる。自社グループ製品のAI(人工知能)化を推進する「知能機械研究センター」を2019年4月に発足させ、次世代製品の開発に向けた研究開発を加速させてきた。同センターの責任者2人にデジタル人材の育成方法や取り組み状況を聞いた。日立造船は1934年5月に設立され、前身の大阪鐵工所を含め140年の歴史を数える。現在は造船事業を分離させて、環境やプラント、社会基盤を主軸事業とする。同社がデジタル人材を必要とする理由の1つが、画像認識技術を用いた検査の自動化や予防保全、機械装置のAI化など、他社製品との差別化である。日立造船 開発本部 技術研究所 知能機械研究センター長の斎藤英樹氏は、「製品販売にとどまらず、高付加価値化や生産性向上を目的としたサービスを付与するのが目的。例えば、化学プラントに設置されている熱交換器は何百本もの伝熱管が溶接されており、内部流体の漏えいにつながる不具合が無いことを確認するために検査が必要だ。日立造船はフェーズドアレイ技術を用いた超音波探傷検査(PAUT)と深層学習による画像認識技術を用いた『AI超音波探傷検査システム』を開発し、伝熱管端部における溶接部の欠陥や損傷を検出している」と説明する。https://japan.zdnet.com/article/35178510/