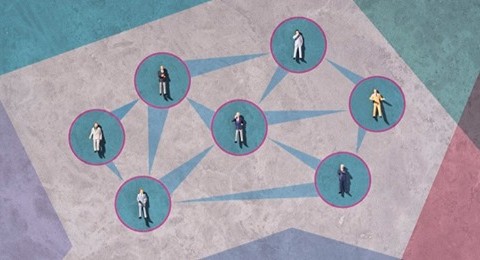デジタル庁の有識者会議「デジタル社会構想会議」の初会合で、有識者からは不足するデジタル人材を「移民」で受け入れるという提言が出てきたわけですが、この提案、日本のDXの状況だけではなく、DXそのものが「なんなのか?」と考えた場合にかなり短絡的でずれている意見なんですよね。
そもそもDX化を一言でいえば「様々な仕事をデジタルでやる」ということなわけで、単に技術だけあっても仕事のデジタル化は簡単にはできないわけです。
なぜかというと、システムやツールを入れるにしても、
どの業務の
どのプロセスを
どのようにデジタル化して
どんな効果を得たいのか
ということを明確化して、「実際に得たい効果」をはっきりさせなければ、その最初の絵が描けないわけです。
「どんな効果」にも様々な切り口があって、
業務のエコシステムを完全に変えてしまうことなのか
一部業務の効率を高めたいのか
ある処理のスピードをあげたいのか
システムの一部をスマホに置き換えたいのか
エラー率を減らしたいのか
要員の業務負担を減らしてより付加価値の高い業務をやってもらいたいのか
というような様々な目的や指標を想定することができるわけですね。
つまり、DXにおいて最も重要なことは、「目的の絵」を描くことであって、単に技術を入れるというわけではないわけです。
技術を担う部隊が国内にいなくても、海外に外注したりすれば可能ですし、サードパーティーのツールを入れることだって可能です。
技術の部分は、実はDX のコアなところではなくて、業務改革やプロセス改善の部分がより重要なわけです。
品質改善や業務改革も、その中心となるのは元々業務に深く関わっている方々で、現場の日々の悩み、アイディア、細かい改善の積み上げが大きな変革に繋がります。外から来た人がドラスティックにやってしまう方法もありますが、宝のようなアイディアは現場にあります。お客様の声を知っているのも現場です。
ですから、既に中にいる人々に対してトレーニングを行って、DXの「構想」に関わってもらった方が、より深い分析と提案が可能になります。現場からは思いがけないアイディアが出てくることもあります。
これは、長年にわたって品質改善で世界のトップだった日本企業が最も得意としてきたことでもあります。今までやってきたことを、今度はデジタルというツールでやるだけなのです。
実は、欧州や北米でDXで先を行っている企業であっても、元々は日本企業の「カイゼン手法」を手本にしていることが多いのです。
ですから今回の提言で、内部の人々の再訓練や教育や支援策に触れていなかったことを非常に残念に思います。