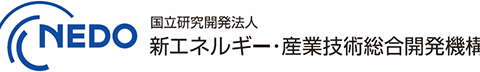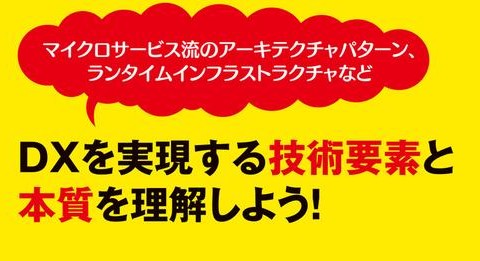スタートアップの成長とともに増えていくのが経営課題。それらを適切に解決し、新たなフェーズの成功につなげる経営チームのあり方とは?グロースキャピタルの目線で、「経営機能の充足度」について考えます。「CxOがどれだけいるか」は重要ではない朝倉祐介(シニフィアン共同代表。以下、朝倉):今回は、レイトステージのグロースキャピタルを運営する立場で、経営チームのどういった点に着目しているかについて、考えてみたいと思います。チーム力の構成要素として、我々は大きく5つの点に注目しています。
今回は「経営機能の充足度」について考えてみましょう。小林賢治(シニフィアン共同代表。以下、小林):レイトステージの上場を見据えたフェーズになると、多くの企業にはいわゆるCxOがいるわけですよね。技術部門のCTOだったり、財務部門を見るCFOだったり。
単にそうした役職の人がいるかどうかではなく、必要なテーマに対する適切な専門性や実行力を持つ人がいるかどうかが重要です。朝倉:そうですね。具体的にCxOなどと呼ばれる人がいればそれで良いかと言うと、決してそうではありません。レイターステージのスタートアップであれば、上場会社として耐え得るような経営を目指すに当たって必要なファンクションを担える人がいるか、しかもそれらをきちんと役割分担してこなせているかといったところが重要なポイントですね。
小林:財務戦略や技術戦略について、しっかり腰を据えて考える能力のある人がいるかどうか。我々はそうした側面を「経営機能」と表現しており、経営体制の中にしっかり取り込まれているかを見ています。トップの「自身の限界に対する認識」をどう生かすか村上誠典(シニフィアン共同代表・以下、村上):スタートアップはどうしても社長への依存度が高いものです。どれだけ機能分化、デリゲーションを進めてきたかは、経営機能充足化に向けたCEOの「トラックレコード」として見ることもできます。小林:経営機能を担える人が組織にいないのは、CEOが代わりになっているからというケースがやはり多い。結果的に属人性が高く、今後の成長に向けてCEOがボトルネックになりやすい様は、よく見られる構造だと思います。朝倉:トップマネジメントに必要な資質を論議した際、4番目に挙げたのが「自身の限界に対する認識」でした。まさに、これの裏返しですね。トップが自らの能力を把握した上で、足りない部分をどのように手当てするか。その結果が端的に表れるのが「経営機能の充足度」だと思います。