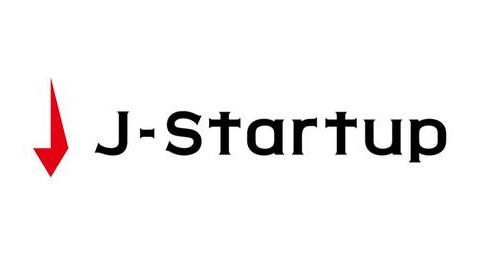どのようなものなのか、予想もつかなかった。筆者は、量子ドットに興味を持っている。微細な粒子で、テレビの輝度や発色に効果を発揮する。そのような物質がどうやって存在するのか、マクロなレベルでは理解しているものの、それを作っている工場となると、果たしてどのようなものが見られるのだろう。科学という名の大釜が煮立っているのはどんな様子で、どのような火が燃えているのか。3人の科学者が、呪文を唱えながらそれをかき混ぜているのだろうか。自分の目で確かめてみたかった。
Nanosysの最高経営責任者(CEO)兼プレジデントであるJason Hartlove氏が、2本の瓶に紫外線を当てているところ。中には、製造工程の段階が異なる量子ドットが入っている
提供:Geoffrey Morrison/CNET
Nanosysは、量子ドットを製造している大手メーカーの1社だ。当然ながら、顧客にどのような企業がいるのか明言しなかったが、おそらく皆さんも同社の量子ドットを使ったテレビを見たことがあるだろう。Nanosysはその量子ドットを何十億も作っている。といっても、数を言ったところで、もちろんあまり説明にはなっていない。量子ドットそのものは、あまりにも微細だからだ。量子ドットを作っているメーカーは他にもあるが、同社の製造工程を見れば、その作り方がよく分かるだろう。
筆者が向かったのは、カリフォルニア州サンノゼにある同社の工場兼研究所だ。科学っぽいものがたくさんあって、小型のビール工場のようなものが見られると予想していた。どちらの予想も、結果的には驚くほど当たっていたことになる。そのときの見学の様子をご紹介しよう。
量子ドットが生まれ、成長して、召喚される場所
少し補足しておくと、量子ドットとは、エネルギーの供給によって発光する微細粒子だ。用途は多岐にわたるが、米CNETとして特筆すべきは、テレビの性能を強化する性質だろう。通常、青色LEDが緑と赤の量子ドットを励起し、LED液晶ディスプレイ(LCD)の性能が、数年前までは不可能だったレベルにまで向上する。映像が明るくなったり、発色も鮮やかになったりするのだ。
最近、サムスンは量子ドットを使って有機LED(OLED)の性能を同じように引き上げ始めている。「CES 2023」では、次世代のディスプレイ技術をかいま見る機会があった。エレクトロルミネセンス方式の量子ドットである。この方式のディスプレイも、数年後には登場しそうだ。量子ドットのみで成り立っており、OLEDやLCDの技術は使われていない。
では、その量子ドットはどうやって製造されているのか。筆者がサンノゼに向かった目的は、それを知ることだった。Nanosysの本社は、これといった特徴のない建物で、市内に無数にあるオフィスパーク風の建築群の一角をなす。工場というよりも、どちらかと言えば、説明できないものを販売するスタートアップ企業が入っている建物のように見える。
各種配合や手法を試験する装置一式の小規模版
提供:Geoffrey Morrison/CNET
中に入れば、よりはっきりと、ここが本格的な場所であることが分かる。安全のためのゴーグルを渡され、研究室に向かう。筆者のような稼業としては、そうした装備を渡してくれるのは、良い兆しだ。大きい建物ではないが、商品が微細粒子なのだから、大きくなくてよいのだ。電子顕微鏡、積分球、試験室などが並んでいるところを抜けていく。筆者が特に気に入ったのは、回転しながら発光している液体の入った球形の大きなガラス器具だ。三角フラスコくらいは知っているという程度なので、恥をかかないように、それ以外のフラスコの名前も必死になって思い出そうとする。思い出せなかったので、黙っていることにした。
Nanosysのマーケティング担当バイスプレジデントを務めるJeff Yurek氏に予告されていたのは、工場が「小型のビール工場のような感じ」に見えるということだった。まさに、そのとおりだ。「反応炉」と呼ばれているステンレス鋼製の大型容器で、発光する複雑な微細粒子の製造に必要な正確な量の各種化学物質が混合され、はき出されている。
Nanosysの量子ドットは無毒性だ
提供:Geoffrey Morrison/CNET
量子ドットの説明としては、中に結晶の入ったナノサイズの「ウィッフルボール」を思い浮かべるといいだろう。それを、複数の工程を経て製造している。最初は、ナノ結晶を成長させる工程だ。このとき、結晶のサイズが重要になる。エネルギーを当てたときに発光する色は、結晶の大きさによって決まるからだ。結晶はもろいので、ウィッフルボールがここで活躍する。結晶の成長を止めてから、さらに化学物質を加えて、結晶を「保護殻」で覆うのだ。この殻には、光子や電子を取り込んで光子を放出できる程度のわずかな開口部がある。具体的な化学物質名、時間、その他いくつかの要素は極秘事項だったが、それは当然だろう。フォトレポートで、画像の一部をぼかしているのも、それが理由だ。
十分に成長してから保護殻で覆った結晶は、いくつものパイプを通る中で洗浄されて排出され、最終的にスチール製のドラム缶に格納される。テレビメーカーにはその状態で出荷され、メーカーによって異なるが、ドラム缶1本で数カ月もつという。テレビ1台あたりに必要な量子ドットは少量だからだ。そのくらい微細で効率的なのである。
Nanosysで使われている加圧チャンバー
提供:Geoffrey Morrison/CNET
最後に立ち寄ったのは研究開発室の1つで、エレクトロルミネセンス量子ドットの研究が進められていた。これまでの量子ドットを使ったテレビ、例えばサムスン、TCLなどが製造している量子ドットLED(QLED)テレビは、フォトルミネセンス方式の量子ドットだった。光エネルギーを、一般的には青色LEDやOLEDから当てると、特定の色で発光するのだが、それ自体では発光しない。
エレクトロルミネセンス量子ドットは、Nanosysでは「NanoLED」と呼んでおり、赤、緑、青の量子ドットを電気だけで発光させる。この方式は、次世代のディスプレイ技術として期待できるだけでなく、他の技術では実現できないさまざまな種類のディスプレイを開発できる可能性がある。
量子レベルのドット
量子ドットの製造方法は、理論的には理解していた。公開されている情報のほとんどは、化学物質についての説明か、あるいは科学者が少量を製造しているところを見せるだけで、産業レベルの説明はなかった。今回の見学ツアーは発見ばかりで、以前から気になっていた、自分の知識の欠けていた部分を埋めてくれるものだった。これほど極小で、しかも複雑なものを、どうやって大量に作るのか、それが疑問だったのだ。蓋を開けてみれば、ビールの作り方と大きくは違っていないようだ。想像もしていなかった。
量子ドットが秘めている可能性は巨大だ。新しいディスプレイ技術としてだけでなく、医療、農業、その他の分野でも期待できる。極小のサイズからすると、そのインパクトはかなりの大きさと言えるだろう。



-480x270.png)