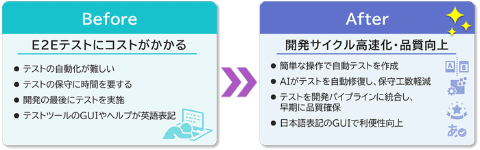ましょう。AGCは、タンク在庫管理システムにより、「ステージ1」でタンク内燃料の検尺をセンサーによってデジタル化し、「ステージ2」でデータを蓄積し、検尺結果を自動的に記録するようにしました。そして、「ステージ3」では、データを分析し、ある一定の状況になった場合にシステム側で自動的に判断して、材料の発注を行うようプロセスを自動化しました。このように、従来人が行っていた判断をシステムに任せることは、現場の熟練技術者の知見を可視化し、組織のナレッジとすることができる他、定形業務をシステムに任せて、人でしかできない業務に人員を集中させることにつながります。ステージ4:複数の業務や企業間のDX共創で生まれる新たな価値このように特定の業務でのDXによる最適化が進んでいくことで、次に見えてくるのが「ステージ4」です。これは複数の業務のDXや、DXが進んでいる企業間による組み合わせによって、今までできていなかった全く新しいやり方が生まれる「新価値創造」のステージになります。ステージ4まで到達しているDX事例日本瓦斯(ニチガス)では、100万軒を超える利用者のスマートメーターに、ネットワーク搭載の検針デバイス「スマート蛍」を取り付け、ガスメーターのリアルタイム検針を実現しています。検針員の月1回の訪問という業務を削減するとともに、代わりに毎日のガスのリアルタイム利用状況のデータを得られるようになりました。DXのはじめの一歩、何から踏み出すべきかここまでご説明したように、IoTはDXのはじめの一歩となる技術です。新たな価値創造をゴールとする場合も、まずはモノのデータ化、データの共有や見える化から始めてください。https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2201/24/news006_4.html